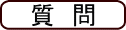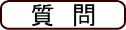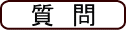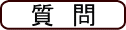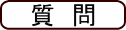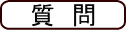jirei-shotokuzei-jouto · 2024/08/17
株式を譲渡した場合は、譲渡益に対して所得税が課税(譲渡所得)されるが、加えてみなし配当に対して課税(配当所得)される場合がある。譲渡所得には20.315%の所得税・住民税等が課税され、配当所得は総合課税の対象となり、最高税率が適用される場合は55.945%の税率で課税される。
jirei-souzokuzei-hyouka · 2023/12/31
被相続人が土地を賃貸し、賃借人がその土地に舗装を施して駐車場として利用していた。被相続人が自ら舗装を行いこれを賃貸していたのであれば土地を事業として貸し付けているのであるから小規模宅地の特例が適用できるが、賃借人が舗装を行った場合は貸付事業用宅地等に該当せず、小規模宅地の特例は適用できないのではないか。
jirei-souzokuzei-hyouka · 2022/07/22
土地と建物の持ち分比率が同一であれば問題はないが、質問のように土地と建物の持ち分比率が異なっている場合は、土地のうち貸家建付地として評価する部分の割合に注意する必要がある。
貸家建付地とは、所有する土地に建築した建物を貸し付けている場合の、その土地ことであるから、土地のうち建物の持ち分に対応する部分のみが貸家建付地として評価される。
jirei-houjinzei-ippan · 2022/05/26
配当や利息にかかる源泉所得税は、少額な場合は租税公課などの費目で損金経理し、法人税申告書別表四で同額を加算した上で、別表一で税額控除が行われる。
しかし、配当の額によっては源泉所得税が多額になり、これを損金経理すると損益計算書の当期利益金額が減少し、対金融機関において好ましくない場合がある。
このような場合は、源泉所得税を損金経理せず、未収還付税金などとして資産計上し、他方で同額を法人税申告書別表四で減算する。
jirei-souzokuzei-ippan · 2021/11/02
相続財産のうちに妻名義の預金があるが、預金の管理が杜撰で、妻の預金なのか被相続人の預金なのか区別できない。両者の預金がごちゃごちゃに入り乱れている。
相続税の申告に当たって、妻の名義預金のうち、被相続人の財産として申告する額を確定させるにはどうすればよいか。
jirei-shotokuzei-jouto · 2021/09/30
デベロッパーから、「住んでいる土地を売ってもらいたい、その土地にマンションを建てるから、土地を手放す代わりに、新築マンションの一室を所有して住んではどうか」という申し出を受けた。デベロッパーは「等価交換」だから税金はかからないというが、本当か。
jirei-souzokuzei-ippan · 2017/07/12
父は平成29年3月1日に、私に1000万円の預金を贈与するという約束をし、父と私とは贈与契約書を交わした。父はその後、3月15日に急死し相続が開始した。私は1000万円の預金を相続すると同時に、贈与契約に基づいて3月30日に父の預金を名義変更して自分名義の預金とした。...
jirei-souzokuzei-ippan · 2017/06/03
私(A)は、平成25年に甲と養子縁組し甲の養子となったが、私には平成20年に妻(甲の血族ではない)との間に生まれた長男乙がいる。養父甲は、乙にも財産を相続させたいと考え、私を養子とした後、乙をも養子とした。甲は平成29年に死亡したが、孫を養子とした場合相続税の2割加算が適用されると聞いている。乙は孫養子として相続税の2割加算が適用されるか。
jirei-souzokuzei-ippan · 2017/06/03
私は、平成28年に甲と養子縁組をし甲の養子になった。甲は平成29年に死亡したが、私は養子縁組前の平成27年に甲から財産の贈与を受けている。相続開始前3年以内の贈与財産は相続税の課税価格に加算しなければならないことは知っているが、養子縁組前の甲と親族関係がない時期に贈与を受けた財産であっても相続税の課税価格に加算する必要があるのか。
jirei-souzokuzei-hyouka · 2017/05/01
当社は非上場の会社だが、社長が死亡したため保険会社から生命保険金10,000千円を受け取り、これを原資として社長の遺族に死亡退職金3,000千円と弔慰金500千円を支給した。尚、この保険は定期付終身保険であり、社長死亡時において貸借対照表には保険積立金1,000千円が計上されていた。この場合、当社の株式の評価に当り純資産価額(評価明細書第五表による)はどのように計算するのか。 生命保険金 10,000千円 保険積立金 1,000千円 死亡退職金 3,000千円 弔慰金 500千円